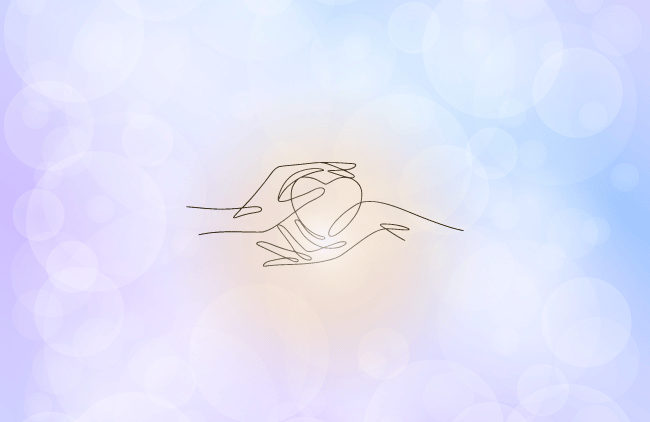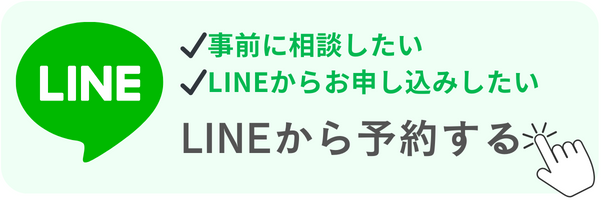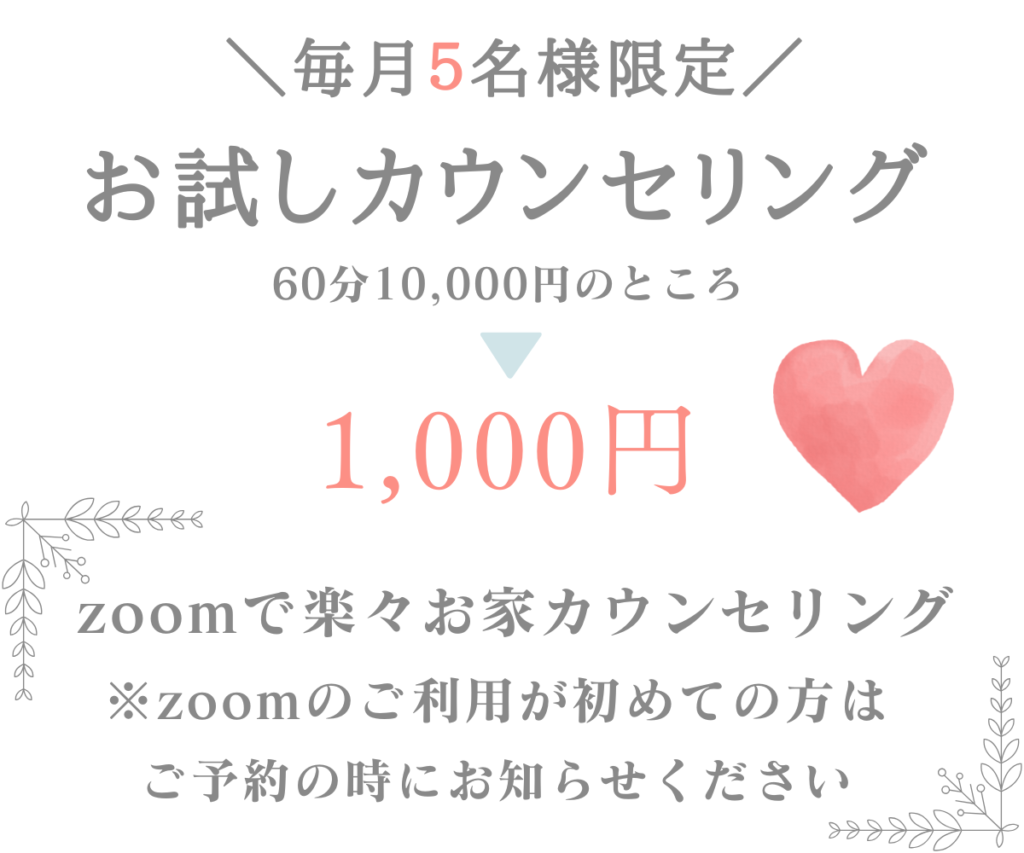この記事を読むと、「どうして自分はこんなにやる気がでないんだ」と自分を責めているアダルトチルドレンや愛着障害の方々が、もっと自分をいたわる必要性に気づけます。
みなさん、こんにちは。『心を育てるカウンセリング』心理カウンセラーの月野瀬みさとです。
みなさんは、どうしてこんなに「なにもやる気になれない」「とにかくすべてが面倒くさい」と身体が動かなかったり、自分の毎日はなんて無意味なんだろうと落ち込んでしまうこと、ありませんか?
そんな自分を「甘えてる」と責めてしまっているかもしれませんが、本当に身体が動かないのは、あなたの「甘え」なんでしょうか?
この状態「怠けてる」と勘違いされがちですが、むしろあなたが頑張り屋で、これまで無理しすぎたのかもしれませんよ。↓動画あり
毒親育ちは「やる気がでない」!?原因と対処法
アダルトチルドレンの「やる気がでない」には理由がある
アダルトチルドレンや愛着障害に悩む方々が、身体が動かなくて、「やる気が出ない」のには、理由があります。
なのに、「頑張れない自分はダメだ」「自分には成長がない」「役に立たない自分には生きる価値がない」と思い込んでおられます。
自分を責めてしまうって苦しいですよね。こうした方々は、親や周りの大人に「もっともっと」って無尽蔵に「親を満足させること」を求められてきた背景があります。自然体の自分でいることが許されずに大人になると、パートナーから「お前使えないな」「あなたって気が利かないよね」と責められたり、上司に「成果をだせ」と求められると、強い不安と焦燥感に駆られて、自分は「無能だ」「価値がない」って何回も何回も自己暗示をかけてしまうんです。
するとね、不思議なくらい身体が動かなくなります。最初は人前ではなんとか動けていても、そのうち、すべてが面倒で、疲れやすくて、いつもだるくなって、最後は全てを投げだしたくなります。
自分を責めずに身体のメッセージに耳を傾けて!
アレルギーが自分の免疫で自分を攻撃するみたいに、親に過剰に責められると自分の中に「内なる批判者」「内なる親」ができて、自分を攻撃してしまうんです。だから、ちょっと人から責められただけで過剰に自分で自分を責めてしまいます。
気楽に、ただのんびりと生きていいのに、頑張りや評価に繋がらない生き方は許されないという「思い込み」があって、セルフケアをしてゆっくり休んでいい時でも、お医者さんやカウンセラーに休めと言われたとしても、「仕事が」とか「もうダラダラ休んでます」って休むことに焦りがでて、全然心が休まらないという盲点になかなか気づけなくなります。
だからね、「情けない」「甘えてる」と考えずに「ああ、神経が疲れてるから、なんにもしたくないんだな」って事実を認めてまず休んで欲しいんです。
これ、コロナなら無駄な抵抗をやめて横になりますよね。怠くなるのは、神経も同じで修復のために身体があなたを強制的に休ませたからなんです。いつまでもやる気が出ないなら「セルフハグの精神」が足りないんだなって知ってて下さいね。
緊張とストレスホルモンと身体の怠さは比例する!?
過緊張の数日後に身体は動かなくなる
子どもの頃、親に怒られるかもって思うとハラハラして気が気じゃありませんでしたよね。自分で自分を責める時も、実は同じように緊張して、ストレスホルモンが出るんです。自責癖があると、常にストレスホルモンが出てる状態なのに、「あ~、明日から仕事かあ」「ああ、あれしなきゃ」ってタスクがあると、近い未来の本物のストレスに備えて、「ストレス抑制ホルモン」がどばどばっと出ます。
元々ストレスホルモンは、身体を俊敏に動かして、敵から身を守ったり逃げたりする運動機能をあげるためのものですから、それが急に下がると身体は動かなくなります。ストレスに備えて「身体を休めろ」と強制終了されちゃうんです。これが「あ~、あれしなきゃ」と思うだけで体が動かなくなる仕組みです。
親に責められることが多かった人は、「ゆっくり休む」とか「ただ何もしない」ことに強い抵抗と罪悪感があります。「頑張ること」と「休んじゃいけない」がセットになっているので、これからは「頑張ったら休む」を当り前にしていきましょう。
「やる気のなさ」って学習される
ところで、やる気のなさって学習して身につくってご存じですか?これ「学習性無力感」って言います。簡単に言うと、強いストレスを感じる環境に長くいると「どうせ抜け出せない」「自分にはムリだ」と学習して、なににも挑戦できなくなるんです。
努力を重ねても望む結果が得られない状況が続いた時に起こります。大きな挫折ではなく、小さな挫折の積み重ねの影響だと言われています。
これは、1967年、心理学者のセリグマンが立証した理論です。彼の有名な実験では、ちょっと可哀想なんですけど、犬をAとBの2グループに分けて、別々の部屋で電気ショックを与えます。
Aの部屋は、犬がスイッチを押すと電流が止まる仕掛みがあって、試行錯誤を経て犬はスイッチを押すようになります。ところが、Bの部屋には犬が何をしても電流がとまらないようになっています。
後日、すべての犬を新しい部屋に入れて、再び電気ショックを与える。そこには低い壁があって、飛び越えれば電気ショックから逃れられるんですが、Aグループの犬は壁を飛び越えて逃げるのに対し、Bグループの犬はじっとうずくまって電気ショックを耐え続けるんです。
つまり、「何をやっても無駄だ」って学習すると無気力になって努力を放棄するようになる。もちろん犬だけでなく、ねずみから人に至るまで、こうした無力感って学習されていきます。

学習性無力感のプロセスとその影響
学習性無力感のプロセス
そのプロセスは、
1.長期間ストレスフルな環境に置かれる
2.抜け出そうとしても上手くいかない経験を繰り返す
3.ストレスを受け入れてしまう
学習性無力感の影響
そのプロセスを経るとこんな特徴が
1.自分と違って周りが凄く見える
2.やる前から自分にはムリだと怖くなる
3.自分の意見や考えに自信がなくなる
4.人から理不尽な言動を受け入れてしまう
5.自分なんてと卑下してしまう
6.人の決めたことに従ってしまう
7.自分のやりたいことや気持ちがわからない
学習性無力感の背景
1.人から否定される環境
「お前使えないな」「そんなこともできないの」と口うるさく言ってくる人がいませんか?
2.あなたの完璧主義
完璧主義と聞くと、なんでも完璧を目指す凄い人と思われがちですが、心理学でいう完璧主義は、自分の不完全さを受け入れられず、人の目を気にして現実的でない理想や無茶な目標設定をして、失敗体験が続き、ますます自信を失っていく状態をいいます。
3.睡眠の質の低下
しっかりと眠ることで、緊張によって疲弊した神経のダメージも修復されます。自律神経の疲労が蓄積すると夜眠れなりますし、逆に身体が神経を修復しようといつも眠たい状態を作り出します。
アダルトチルドレンの学習性無力感「やる気がでない」の5つの対処法
安心して頂きたいのは、この学習性無力感はセルフハグ精神=自分に優しく接する気持ち)が育てば、自分の中から元気が湧いてきて、克服できます。
1.まずは環境のせいにしてみる
付け加えると、一旦とか一時的にということなんですが、学習性無力感のある人は、基本的に酷い自責癖があります。自分を責めすぎるから、根本の原因も把握できていません。
まずは、環境のせいにして、あなたを批判しすぎている人がいないかを観察して、環境を改善します
2.すべての人に挫折はあると理解する
自分の尊敬する人に、人生の挫折と克服方法を聞いてみて、「どうして自分はついていないんだ」「自分ばっかり」という自分への暗示をといてあげます。
3.同じ経験を克服した人と話す
成功した人の話を聞いて参考にします。自助グループなどで少し回復が進んだ人の話を聞いたり、生きづらさを克服したカウンセラーに心の回復のプロセスを教わって、情報を集めます。
4.自分を大事にする
セルフハグ精神は自己肯定感を育ててくれます。自分を責めず沢山褒める。ちょっとした成功体験を見過ごさないで、一日の終わり布団の中なんかで、ちゃんと自分のできたことを認めてあげてください。
5.しっかり眠る
よく眠るための生活の工夫をします。少し回復してきたら、軽い運動もおススメです。暖かいお風呂や日光を浴びる、身体にいい食事を腹八分目でとるなど、眠りを促すものを生活に取り入れてください。

自分のやり方があっているのかがわからなくなって不安になることもあると思います。
そんな時はひとりで悩まず、いつでも声をかけてくださいね。
あなたは幸せになっていい。
あなたが幸せになることを止める権利は誰にもありません。
生きづらさを手放して、自然体のあなたで生きていけることを、心から応援しています。